岡本先生と共に味わう讃美の力 (14)讃美歌298番 「安かれわがこころよ」(フィンランディア)、 ~シンシナティ日本語教会主催
願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。
願わくは主がみ顔をもってあなたを照し、あなたを恵まれるように。
願わくは主がみ顔をあなたに向け、あなたに平安を賜わるように。
(民数記6:24-26、新改訳2017)日本聖書協会『口語訳聖書』民数記 6章24-26節
【↓】Y.Tさんによるヴァイオリン独奏動画 へのリンク
♪ https://www.youtube.com/watch?v=3mesrwYpfp4 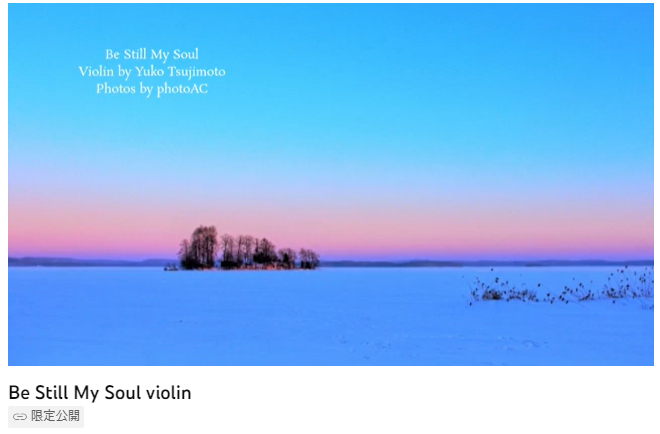
■ 1.はじめに
今回取り上げる讃美歌番298番 「安かれわがこころよ」(Be still, my soul)は、「Be still!、静まれ、やすかれ、わが心よ」、「あなたにどんな悲しみ苦しみがあろうとも神を信頼していなさい、主はあなたの友です味方です」と私たちを慰め励ましてくれます。
この讃美歌についての解説を梅染信夫氏が書かれていますが、その冒頭で、この讃美歌と聖書の解き明かしにより人生が一変した女性について次の様に紹介しておられます。
彼女は大学で学ぶうちに、漠然とした不安と焦燥感を感じ将来社会人としてどうやっていけるのか悩み始めたそうです。その彼女が出席したある主日礼拝で、イザヤ30:15④から説教を聞き、この “Be Still, My Soul”を歌ったことがきっかけで、主イエスが最良の友として自分と共におられることに気づいたのです。そして主の御声を聞いたのです。「あなたが負う十字架の痛み苦しみに耐えよう、神に信頼しあなたの人生を委ねよう」と。
この様に、讃美歌298番 「安かれわがこころよ」(Be still, my soul)と、歌詞にちりばめられた珠玉の御言葉は、多くの人々を慰め励まし、平安で満ち足りた人生へと、今日もなお導き続けています。
■ 2.讃美歌289番誕生の歴史 (資料1参照)
(1)メロディーの誕生(1899年)
この讃美歌のメロディーは、シベリウスの有名な交響詩『フィンランディア』 (Finlandia)作品26が元になっています。当時フィンランドでは帝政ロシアからの独立の機運が高まっており、その国民の愛国心がこの曲に込められたのですが、帝政ロシア政府によ演奏禁止処分を受けました。
(2)原歌詞(ドイツ語)の誕生(1752年)
ルター派女子修道院院長カタリーナ・フォン・シュレーゲルにより「Stille, mein Wille! dein Jesus hilft siegen」と言うドイツ語の詩が誕生しました。
(3)英語訳詞の誕生(1855年)
スコットランドの作曲者ジェーン・ボースウイックがドイツ語から英訳して"Be Still, My soul"となりました。
(4)詩 "Be Still, My soul" と「フィンランディア」を組み合わせた讃美歌の誕生(1932年)
アメリカ長老派教会の賛美歌集The Hymnal(1933)の編集委員会が、「フィンランディア」の編曲をシベリウスに依頼しました。そして今日、シベリウス作曲・編曲による讃美歌で私たちも賛美するのです。
■ 3.讃美歌にちりばめられた御言葉の探求
では、讃美歌にちりばめられた御言葉を探求してまいります。大野野百合氏が和訳されたボースウィックによる英語歌詞(資料2)を手掛かりにして進めますが、そのボースウィックの英訳歌詞が出版された時、冒頭に、十字架を目前にした主イエスの言葉が掲載されていたそうです。それは、
① ルカ21:19 あなたがたは、忍耐することによって自分のいのちを勝ち取りなさい。
福音書を精読していると、主イエスが弟子たちを教える仕方の特徴に気づかされます。まず、ご自身が父なる神に聞き、神との関係に生き、それをお手本として、「あなたがたもこの様にして私についてきなさい」と教えておられます。
この事を思うとき、①ルカ21:19の御言葉は、十字架を目前にした御子イエスを励ます父なる神の言葉であり、その言葉を主イエスは私たちにも教えられたのです。ですから、ルカ21:19の御言葉がボースウィックの英訳歌詞の出版に際して冒頭に掲げられていたことは、実に意義深いことだと思います。
■ 一節以降で反復される 「静まれ (be still)」
静まれ、わが心よ、主はあなたの味方です。
悲嘆、苦痛の十字架を耐えしのびなさい。
命令したり、前もって用意することは、主に任せなさい。
どんなに状態が変わっても、主は誠実であられる。
~ ♪ - ♪ - ♪ ~
引照聖句として最も良く知られているのは
② 詩篇46:10 「やめよ(Be still)。知れ。わたしこそ神。わたしは国々の間であがめられ地の上であがめられる。」
ですが、神の民が万事窮しておじ惑う時にも、主は「Be still」と言われます。有名な紅海渡渉の出来事の直前、エジプトの軍勢が背後に迫っているのを見て騒ぎ立つ民に、神がモーセを通して語った言葉もそうです。
③ 出エジ14:14 【主】があなたがたのために戦われるのだ。あなたがたは、ただ黙っていなさい(be still)。」
また、国が歴史上希に見る凶悪なアッシリヤの脅威に曝された時、預言者イザヤを通して主は語られました。
④ イザヤ30:15 イスラエルの聖なる方、【神】である主はこう言われた。「立ち返って落ち着いていれば、あなたがたは救われ、静かにして信頼すれば、あなたがたは力を得る( in quietness and trust is your strength)。」しかし、あなたがたはこれを望まなかった。
国難に瀕して他国と同盟を結び危機を脱しようと図ることは、ある意味当然です。しかしこの時問題だったのは、神を信じる民でありながら神の御旨と助けを祈り求めなかったことでした。
そして主は、私たちが“人生の謎”に困惑する時にも「Be still」と言われます。その謎とは、「悪を行う者が私たちが腹を立て妬むほどに繁栄することがある」ということです。
⑤ 詩 37:7 【主】の前に静まり(Be still)耐え忍んで主を待て。その道が栄えている者や悪意を遂げようとする者に腹を立てるな。
⑥ 詩篇4:3-4 知れ。【主】はご自分の聖徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき【主】は聞いてくださる。/震えわななけ。罪を犯すな。心の中で語り床の上で静まれ。
⑦ エペソ4:26-27 怒っても、罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけません。/悪魔に機会を与えないようにしなさい。
私たちの怒りにはそれなりの理由があります。しかし、主の愛が注がれている私たちは罪を犯してはならないのです。もし罪に気づいたら、泥沼に引きずり込まれぬよう主イエスのもとに逃れ速やかに悔い改めるのです。ですが現実には、「はい、じゃあそうします」とはなかなかなりません。でもそういう時も「Be still!、静まれ、やすかれ、わが心よ、主はあなたの味方です。」と自分を説得し続けてみませんか。
■ 歌詞 一節
静まれ、わが心よ、主はあなたの味方です。
悲嘆、苦痛の十字架を耐えしのびなさい。
命令したり、前もって用意することは、主に任せなさい。
どんなに状態が変わっても、主は誠実であられる。
わが心よ、静まれ、あなたの最高の天の友は、
いばらの道を通して、喜ばしい結果に導きたもうのです。
~ ♪ - ♪ - ♪ ~
ここでは、「〈主はあなたの味方〉〈最高の天の友〉だよ、だから自分の十字架を背負って安心してキリストに従っていこう!」と〈わが心〉を励ましています。
⑧ マタイ16:24-25 …「だれでもわたしについて来たいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負って、わたしに従って来なさい。/自分のいのちを救おうと思う者はそれを失い、わたしのためにいのちを失う者はそれを見出すのです。
また一節の最後、〈いばらの道を通して、喜ばしい結果に導きたもう〉は、次の御言葉の要約です。
⑩ ヘブル12:10-11 肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことにしたがって私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の聖さにあずからせようとして訓練されるのです。/すべての訓練は、そのときは喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます。
⑪ 詩篇116:7 私のたましいよおまえの全きいこいに戻れ。【主】がおまえに良くしてくださったのだから。
「Be still!、静まれ、やすかれ、わが心よ」です。
■ 歌詞 二節 1~4行目
静まれ、わが心よ、神は過去にあなたを導かれたように、
未来も導きたもうのです。
何事もあなたの希望、信頼をくじくことがないように。
今神秘的に見えるすべてのことが、最後には明らかになります。
~ ♪ - ♪ - ♪ ~
二節では永久に変わる事が無い神の御性質が歌われています。これは私たちの信仰の大黒柱です。
神はこれ迄も信仰者のために働き導いてこられた。このお方は今後も同様になさる、と言う事です。
しかし残念な事に、私たちはその事が頭では判っていても、物事を近視眼的に見てしまい実感が湧いてこないので、なかなか生活が伴いません。この様な私たちに主は言われます。
⑭ Ⅰコリント13:12 今、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、そのときには顔と顔を合わせて見ることになります。今、私は一部分しか知りませんが、そのときには、私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。
ですので、「Be still!、静まれ、やすかれ、わが心よ」です。
■ 歌詞 二節 最後の二行
静まれ、わが心よ、嵐の風、波は主のみ声を聞きわけます。
地上でそれらを主は静められたのです。
~ ♪ - ♪ - ♪ ~
これはあの有名な情景を歌っています。
⑮ マルコ4:39, 41 イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に「黙れ、静まれ」("Quiet! Be still!")と言われた。すると風はやみ、すっかり凪になった。//彼らは非常に恐れて、互いに言った。「風や湖までが言うことを聞くとは、いったいこの方はどなたなのだろうか。」
イエスは、ただのひと言で自然界を治められました。嵐の風、波ですらイエスのみ声を聞きわけました。
ですが、この時の弟子たちは「いったいこの方はどなたなのだろうか」と怖れたのです。
しかし私たちはもう怖れることはありません、主イエスは私の味方、友でありまことの神だと知ってるからです。
ですので、「Be still!、静まれ、やすかれ、わが心よ」です。
■ 歌詞 三節
静まれ、わが心よ、最愛の友人たちがこの世を去り、
涙の谷ですべてが暗黒に見えるとき、
あなたは主の愛、み心をより良く知ることができます。
主はあなたの悲しみと恐怖を取り去ってくださいます。
静まれ、わが心よ、あなたの主イエスは、
彼が取り去られたものを豊かに返してくださいます。
~ ♪ - ♪ - ♪ ~
作詞者は自分の苦悩を旧約聖書に登場するヨブに重ねたのでしょう。
ヨブは全ての息子娘を失います。その時ヨブは、
⑯ ヨブ1:21 …「私は裸で母の胎から出て来た。また裸でかしこに帰ろう。【主】は与え、【主】は取られる。【主】の御名はほむべきかな。」
と、信仰に立ち続けます。ところが、その後立ち続けに全財産を失い、苦痛に苛まれる酷い病気に掛かり、信頼する妻には裏切られ、見舞いに来た友人たちからは因果応報的に激しく責め立てられるに至って、ヨブは神の“仕打ち”に抗議します。
しかし主は、「涙の谷」(詩篇84:6)を通ったヨブに、苦難の背後には人には知り得ない神の深い思いがあることを教え、「自分を責めず、神をも責めず、神を信頼し続けるように」と懇(ねんご)ろに語りかけます。そして主はヨブを「闇と死の陰から導き出し」(詩篇107:14 )悔い改めへと導き、主は「ヨブの後の半生を前の半生に増して祝福され」(ヨブ42:10, 12)ました。
この三節の歌詞は、旧約聖書に記された、とてつもない苦難を通ってきた信仰者のドラマを思い起こさせつつ、私たちを「Be still!、静まれ、やすかれ、わが心よ」と励まします。
詳しい解説は割愛しますが、ヨブの生涯における試錬とその後の祝福は、主イエスの地上の御生涯を暗示しています。
父なる神は、御子イエスに十字架に至る苦難の生涯を歩ませられ、最後に十字架上で私たちの罪の贖いとしてイエスの命をも奪われました。しかし父なる神はイエスを墓からよみがえらせられました。
その主イエスは言われました。
⑱ ヨハネ20:19-20 …「平安があなたがたにあるように。」/こう言って、イエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。
三節の歌詞も新約聖書全体も、〈彼が取り去られたものを豊かに返してくださ〉ることの確かさを歌っています。
■ 歌詞 四節
静まれ、わが心よ、私たちが主のみそばにはべる時は
迫っています。
失望、悲嘆や恐怖が去ると、悲しみは忘れ去られ、
愛の純粋な喜びがもどってきます。
静まれ、わが心よ、変化と涙が過ぎ去るとき、
私たち皆は、安全で祝されて、最後に会うことができます。
~ ♪ - ♪ - ♪ ~
四節に関して、一つの聖句を簡単に解き明かしさせていただきます。
⑲ ゼカリヤ2:13 すべての肉なる者よ、【主】の前で静まれ(Be still)。主が聖なる御住まいから立ち上がられるからだ。」
ゼカリヤは、バビロン捕囚から帰還した神の民に主の言葉を伝えた預言者ですが、そのゼカリヤの名前には、「主は覚えて下さる」の意味があります。神はご自身の契約を「覚えて下さり」、それを実現するために行動されることを証しているのです。
詳しい話は省きますが、ゼカリヤ書は時間的に二つのことを語っています。まず、私たちにとっては過去の出来事となったエルサレム神殿の再建とメシヤの到来による救いです。そしてもう一つ同時に語っていることは、私たちにとって未来のこと、黙示録にも啓示されている新しい天と地のことです。
神は永久に変わらぬお方で、過去に為された御心は、これから先にも成し遂げられます。
ですので、私たちは「Be still!、静まれ、やすかれ、わが心よ」と確信と喜びを持ってこの讃美歌を歌えます。
■ 歌詞 五節
静まれ、わが心よ、賛美の歌を、
地上で高きにいます主に歌いはじめましょう。
あなたの言動において、主を認めなさい。
そうすれば主はあなたに喜びのまなざしを向けられます。
静まれ、わが心よ、聖なる命の太陽は
雲間からさらに輝かしく照るでしょう。
~ ♪ - ♪ - ♪ ~
この讃美歌の最終節は、私たちを礼拝へと招いて終わりの日に完成する御国(㉒ 黙示録21:23)を仰ぎ望ませ、そして祝祷(㉓ 民数記6:24-26)により平安を与え、私たちを日々の生活へと送り出します。
前半は、四節と同様バビロン捕囚から帰還間もない、主の日の礼拝での出来事を呼び起こします。
その時、ネヘミヤはバビロン捕囚から帰還した民に聖書を解き明かしました、捕囚は背信に対する神の裁きであったことを。すると民は悲しみの涙にくれたのです。その民にネヘミヤはこう励ましたのです。
㉑ ネヘミヤ8:10-11 …今日は、私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。【主】を喜ぶことは、あなたがたの力だからだ。」/レビ人たちも、民全体を静めながら言った。「静まりなさい(Be still)。今日は聖なる日だから。悲しんではならない。」
御言葉はしばしば聞く者の心を鋭く刺し貫き深い罪の自覚をもたらします。しかし、悔い改めて〈【主】を喜ぶことは、あなたがたの力〉になるのです。
歌詞三行目では、次の箴言を引用しています。
⑳ 箴言3:5-6 心を尽くして【主】に拠り頼め。自分の悟りに頼るな。/あなたの行く道すべてにおいて、主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる。
冒頭で、人生が一変した女性の事をお話しました。彼女が「あなたが負う十字架の痛み苦しみに耐えよう、神に信頼しあなたの人生を委ねよう」との御声を聞いて御言葉への聴従を決断した時、主はこの御言葉をこの女性に成就されました。さらに主は祝祷(㉓ 民数記6:24-26)で、彼女を新たな人生へと送り出されたのです。
■ 結びの奨励と祝祷
「どんな悲しみや苦しみ、怒りや怖れがあっても、神に深い信頼をおきなさい」と、フィンランディアの調べにのせて「静まれ、安かれ」と主イエスは私たちを招いておられます。
シベリウスは祖国の生みの苦しみの中で作曲し、作詞者も筆舌に尽くし難い苦悩の中にあって、聖書に主イエスの地上の御生涯と御国での栄光を見、声を聞き、詩を書いたことが伺われます。
ロシアによるウクライナへの軍事侵攻のあと、フィンランドの市民がこうつぶやいたそうです。
「私たちが何も恐れずに、平和な時代に生きているのは、特別なことなのかもしれない。私たちの親や祖父母の世代はこんなぜいたくは享受できなかった」
(出典:「北欧フィンランド 隣国ロシアに脅かされて」 https://www3.nhk.or.jp/news/special/international_news_navi/articles/qa/2022/06/28/23255.html )
フィンランドとロシアとの国境は約1300キロ、実に札幌~福岡間の直線距離と同じくらいの長さです。シベリウスが作曲した後のフィンランドはロシアの脅威にもかかわらず、軍事的中立を保ち、国連の2022年「世界幸福度報告書」では、5年連続となる1位に選ばれています。そのフィンランドが、ロシアのウクライナ侵攻を契機に中立からNATO加盟へと国策を転換したのです。
私たちは、この讃美歌を自分の歌として歌える幸いを感謝しつつ、フィンランドやウクライナの方々ばかりでなく、この讃美歌と御言葉に拠る慰めと励まし、「静まりなさい(Be still)」 を必要とする隣人の為にも祈っていこうではありませんか。
㉓ 民数記6:24-26により祝祷致します。
願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。
願わくは主がみ顔をもってあなたを照し、あなたを恵まれるように。
願わくは主がみ顔をあなたに向け、あなたに平安を賜わるように。
アーメン
■ 参考文献・資料
・大塚野百合 著 『「主われを愛す」 ものがたり』、教文館、2013/1/10 P.60ff
・梅染信夫 著 『神は愛なり 讃美歌物語3』 新教出版社、1994/6/30 P.76ff
