岡本牧師と共に味わう讃美の力 (第39回) ~讃美歌406番「友とわかるる」 ~シンシナティ日本語教会主催
雀さえも住みかを 燕もひなを入れる巣をあなたの祭壇のところに得ます。万軍の【主】私の王私の神よ。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは。彼らはいつもあなたをほめたたえています。セラ
(詩篇84:3-4 、 新改訳2017)
日本聖書協会『口語訳聖書』詩編 84編3-4節
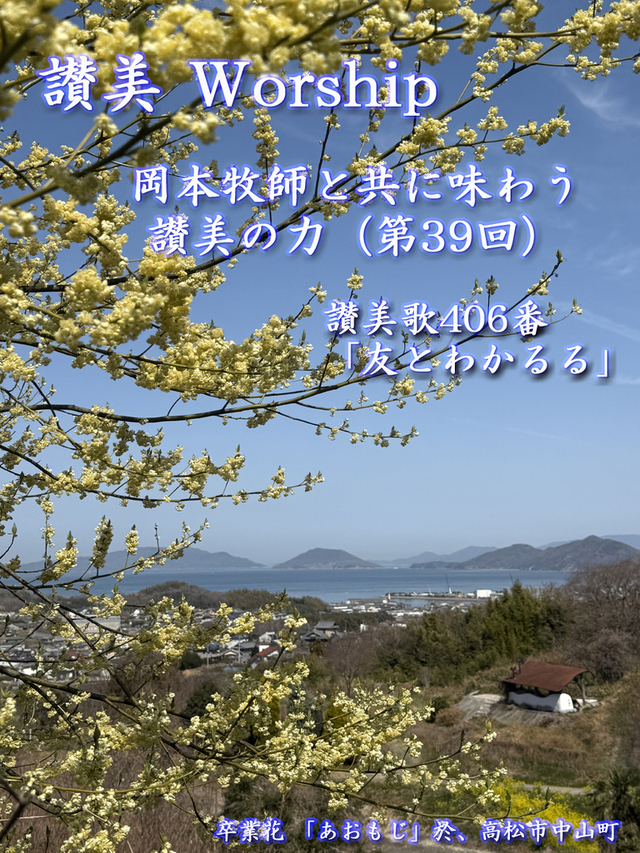
三月といえば卒業式など別れの季節でもあります。近年は大都市の公立学校(特に小学校)を中心に、かつての卒業式定番曲『仰げば尊し』ではなく、その時々の流行曲を歌う学校が増えてきているそうです。
その様な時代の風潮の中で、ミッションスクールの卒業式前日燭火礼拝等で歌われる讃美歌が、今回取り上げる讃美歌406番「友とわかるる」です。この讃美歌は、メンデルスゾーン「6つの歌op.59」の第3番「緑の森よ」のメロディーに、第九代青山学院院長を務められた豊田實(1885-1973)が、彼の恩師であり『国際基督教大学(ICU)創立史』を執筆したC.W.アイグルハートとの別れを念頭において作詞(1953年)したものです。
ところで春の別れは卒業式ばかりではありませんね。
進学や就職、家庭の事情による転居、また結婚などにより、これまで手塩にかけて育ててきた子どもたちや青年たち、教会員を送り出す教会の想いを思うと、本当にこの讃美歌が心に染みます。
また、私事ではありますが、私の父と母の出生を証明する戸籍謄本を最近取り寄せました。そこでは、死亡により両親ばかりか叔父や叔母たちも皆除籍されていましたし、私自身が戸主の戸籍からは結婚により娘たちが除籍され私たち夫婦二人だけになっていました。
そういう自分もいずれ別れを告げることになりますが、「私たちの国籍は天にあ」る(ピリピ3:20)恵みを覚えつつ、聖書に記されている惜別の祈りや祝祷の如く、私の家族や孫たちを今のうちに祝福しておきたいと願っています
前置きが長くなりましたが、本題に入ります。
「友とわかるる つどいなれば こころにかかる 雲はあれど」と、深い惜別の情が吐露されつつも同信の友ゆえの希望がみなぎり、祝福の祈りすら込められた讃美歌406番「友とわかるる」に導かれて御言葉を瞑想してまいりましょう。
■ ♬~ 一節
友とわかるる つどいなれば
こころにかかる 雲はあれど
はるけき里に 夢路かよい
おもいをはこぶ つばさもあり
「おもいをはこぶ つばさもあり」とはどんな意味でしょう。
「おもい」とは、神様への祈りとなって現れる私たちの想いのことで、「つばさ」は、父なる神の力強さを「鷲の翼」にたとえた聖句に拠っているのでしょう。
_†_ ① 申命記32:10-12 _†_
32:10 主は荒野の地で、荒涼とした荒れ地で彼を見つけ、これを抱き、世話をし、ご自分の瞳のように守られた。
32:11 鷲が巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、翼を広げてこれを取り、羽に乗せて行くように。
32:12 ただ【主】だけでこれを導き、主とともに異国の神はいなかった。
神が、ご自身の民イスラエルを罪と死の支配から解放した「出エジプト」の御業を言っています。
同時に私たちが心に留めたい事は、主イエスはこの御言葉を引用して、頑なな民イスラエルの背信と罪深さを嘆かれた(マタイ23:37) ことです。
_†_ ② マタイ23:37-38 _†_
23:37 エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に遣わされた人たちを石で打つ者よ。わたしは何度、めんどりがひなを翼の下に集めるように、おまえの子らを集めようとしたことか。それなのに、おまえたちはそれを望まなかった。
23:38 見よ。おまえたちの家は、荒れ果てたまま見捨てられる。
■ ♬~ 二節
♬~ 二節1行目
すべていずこも 父のすまい
神は時間と空間を超越して、すべての存在に内在しておられること、「神の遍在」を歌っています。
聖書は遍在される神についてこう記します。
_†_ ③ エレミヤ23:23-24 _†_
23:23 わたしは近くにいれば、神なのか。──【主】のことば──遠くにいれば、神ではないのか。
23:24 人が隠れ場に身を隠したら、わたしはその人を見ることができないのか。──【主】のことば──天にも地にも、わたしは満ちているではないか。──【主】のことば。
_†_ ④ イザヤ57:15 _†_
57:15 いと高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名が聖である方が、こう仰せられる。「わたしは、高く聖なる所に住み、砕かれた人、へりくだった人とともに住む。へりくだった人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。
かつてのエルサレム神殿のすずめの巣、つばめの巣は、安全・安住のすみかでした。
_†_ ⑤ 詩篇84:3-4 _†_
84:3 雀さえも住みかを 燕もひなを入れる巣をあなたの祭壇のところに得ます。万軍の【主】私の王私の神よ。
84:4 なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは。彼らはいつもあなたをほめたたえています。セラ
イエス様は言われました、「空の鳥を見なさい」(マタイ6:26)。あんなに小さな小鳥すら、種まきも刈入れもしないのに、神は御目を注ぎ、愛を注ぎ、神の許しがなければ一羽たりとも地に落ちないではないか、と。
小さく弱い私たちでも、心砕かれ謙る人は遍在される神の家に安住させていただけます。「すべていずこも 父のすまい」となります。
♬~ 二節2~4行目
とまるもゆくも ただ御旨に
ゆだねしひとの くしき平和
友をまもれと 我らいのる
「とまるもゆくも」との歌詞は、かつての卒業式定番曲『蛍の光』を思い出させますが、この讃美歌では「残る人も別れ行く人も、お互い思うことは数限りなくあります。けれども、私たちは、神の御旨、すなわち神の意志・好意に委ね、くすしい平和をいただいて、友を守ってくださいと祈れるのです!」と歌います。
神の御旨に委ね心に平安をいただき祈れる幸い、おそらく皆様も、きっと込み上げて来るものをお持ちでしょう。
■ ♬~ 三節
地なるこの世を 超えてたかき
あめなるみやこ あおぎ望み
旅路をたどる われらなれば
うたのしらべも 祈りも合わん
この三節は、別れを経て人生の旅路を辿り行く私たちを、ヘブル11章の「信仰の人」「地上では旅人であり、寄留者」に重ねています。
_†_ ⑥ ヘブル11:13-16、39-40 _†_
11:13 これらの人たちはみな、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。
11:14 そのように言っている人たちは、自分の故郷を求めていることを明らかにしています。
11:15 もし彼らが思っていたのが、出て来た故郷だったなら、帰る機会はあったでしょう。
11:16 しかし実際には、彼らが憧れていたのは、もっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は、彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。
...
11:39 これらの人たちはみな、その信仰によって称賛されましたが、約束されたものを手に入れることはありませんでした。
11:40 神は私たちのために、もっとすぐれたものを用意しておられたので、私たちを抜きにして、彼らが完全な者とされることはなかったのです。
この三節最終行では 「うたのしらべも 祈りも合わん」、すなわち、讃美も祈りも同じ思いですと歌っていますが、誰と誰が同じ思いなのでしょうか。
私は思うのです。別れの場にいる友だけでなく、場所や時間を超えて「天の星のように、また海辺の数えきれない砂のよう」(ヘブル11:12)な「信仰の人たち」にも想いを馳せながら、彼らと同じ思い、一つ思いなんだ!と歌っている、と。
これは実に天的な素晴らしさです。調和や一致よりも、分断と対立が声高に叫ばれる現代にあってはなおさらです。創世記11章にはバベルの塔の出来事が記されています。「全地は一つの話しことば、一つの共通のことばであった」(創11:1)。しかし、「さあ、われわれは自分たちのために、町と、頂が天に届く塔を建てて、名をあげよう。…」(創11:4)としました。いわゆる自国第一主義の先駆けです。その時、「【主】が全地の話しことばを混乱させ…た」(創11:9)、神は彼らを裁き混迷の時代を来たらせられました。
しかし、私たちは言葉も生活環境も違っていても、「うたのしらべも 祈りも合わん」、主にあるが故に一致できるのです。
さて次に四節です。聖書には、別れに際しての祝祷が幾つも記されてますが、この四節全体も祝祷です。
■ ♬~ 四節
♬~ 四節1行目
かたく結べる この友がき
冒頭に「友がき」という聞き慣れない言葉が出てきますが、友と交わりを結ぶことを、垣を結(ゆ)うのに例えた言葉です。「垣根」を作る時に横棒で支え棕櫚縄(しゅろなわ)で結束した如く、絆の強い友との交わりが「友がき」です。
この「友がき」を、皆さまも口ずさんだことがあるはずです。それはこの曲です。
♬~ 唱歌 『ふるさと』
1 兎追いし、かの山、子鮒釣りし、かの川、
夢は今も巡りて、忘れがたきふるさと。
2 いかにいます父母、つつがなしや友がき、
雨に風につけても、思いいずるふるさと。
3 こころざしをはたして、いつの日にか帰らん、
山はあおきふるさと、水は清きふるさと。
私もこの唱歌 『ふるさと』が大好きですが、誠に残念なことですが、この歌で歌われている故郷の原風景は日本から急速に失われつつあります。私たちが「帰ってみたいなあ」と思っても、殆どの場合私たちが出て来た故郷は変わり果ててます。
この現実を目の当たりにすると、先ほどのヘブル11章で「もっと良い故郷、すなわち天の故郷」が約束されていることの幸いに驚嘆せずにおれません。
しかもヘブル11:40に「(その故郷は)私たちを抜きにして」は成り立ち得ないとあります。私たちが様々な別れを経験しようとも私たちは「友がき」とされています。その「友がき」をかたく結ぶのは主イエスが賜わる愛です。
_†_ ⑦ ヨハネ15:12-17 _†_
15:12 わたしがあなたがたを愛したように、あなたがたも互いに愛し合うこと、これがわたしの戒めです。
15:13 人が自分の友のためにいのちを捨てること、これよりも大きな愛はだれも持っていません。
15:14 わたしが命じることを行うなら、あなたがたはわたしの友です。
15:15 わたしはもう、あなたがたをしもべとは呼びません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。わたしはあなたがたを友と呼びました。父から聞いたことをすべて、あなたがたには知らせたからです。
15:16 あなたがたがわたしを選んだのではなく、わたしがあなたがたを選び、あなたがたを任命しました。それは、あなたがたが行って実を結び、その実が残るようになるため、また、あなたがたがわたしの名によって父に求めるものをすべて、父が与えてくださるようになるためです。
15:17 あなたがたが互いに愛し合うこと、わたしはこれを、あなたがたに命じます。
次に、四節2行目以下ですが、詩篇103編を敷衍して歌っています。
_†_ ⑧ 詩篇103:15-17 _†_
103:15 人その一生は草のよう。人は咲く。野の花のように。
103:16 風がそこを過ぎるとそれはもはやない。その場所さえもそれを知らない。
103:17 しかし【主】の恵みはとこしえからとこしえまで主を恐れる者の上にあり主の義はその子らの子たちに及ぶ。
とありますが、「とこしえからとこしえまで」変わることが無い主の恵みを歌います。
♬~ 四節2、3行目
みめぐみの花 色はあせず
かおりをふかく こころにしめ
_†_ ⑧ 詩篇103:20-22 _†_
103:20 【主】をほめたたえよ主の御使いたちよ。みことばの声に聞き従いみことばを行う力ある勇士たちよ。
103:21 【主】をほめたたえよ主のすべての軍勢よ。主のみこころを行い主に仕える者たちよ。
103:22 【主】をほめたたえよすべて造られたものたちよ。主が治められるすべてのところで。わがたましいよ【主】をほめたたえよ。
この御言葉を受けた祝祷で讃美がとじられます!
♬~ 四節4行目
さちあれ友よ 主につかえて
それぞれが新しい道に踏み出して行く「別れ」の場には、離ればなれになる寂しさや感謝と言った様々な思いが交錯しますが、究極は「お互い幸せでね」との祈り心ではないでしょうか。
この事を神に信頼し委ねて歌うこの讃美歌を、私は生涯歌い続けると思います。皆さまの心と口からも、「さちあれ友よ、主につかえて」との祝福が溢れて広がり行くことを願ってやみません。
