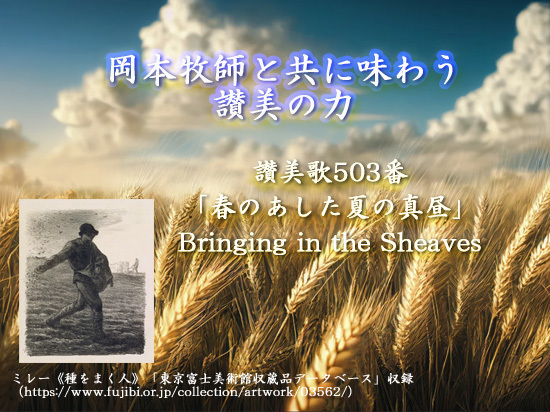岡本牧師と共に味わう讃美の力 (第43回) 讃美歌503番 「春のあした夏の真昼」Bringing in the Sheaves ~シンシナティ日本語教会主催
涙とともに種を蒔く者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰って来る。
(詩篇126編5-6節)日本聖書協会『口語訳聖書』詩編 126編5-6節

■ 序
今回取り上げる讃美歌は、讃美歌503番「春のあした夏のまひる」で、神戸にお住まいのS姉の愛唱歌です。
この讃美歌は、直接的には種蒔きの苦労と収穫を待望した喜びを歌っています。そのリフレイン(繰り返し)部分は、『大草原の小さな家』という、古き良きアメリカの開拓時代に様々な困難を乗り越えるインガルス一家の姿を通して家族愛や人間愛の尊さを描く不朽の名作の様々な場面で歌われました。
事実、西部開拓時代の終盤に創られたこの讃美歌は、当時の伝道集会で歌われ多くの開拓民を救いに導き、今もなお、信仰に生きる私たちや伝道者の励みになっている讃美歌です。
参考URL: https://www2.nhk.or.jp/archives/articles/?id=C0010353
今日も、皆さまと讃美歌と御言葉の恵みを分かち合って参りましょう。
■ 1節
Sowing in the morning, sowing seeds of kindness,
Sowing in the noontide and the dewy eve;
Waiting for the harvest, and the time of reaping,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
〈Sowing in the morning, …in the noontide and the dewy eve;〉
一行目二行目は、
_†_ ① 伝道の書(コヘレト)11:1, 4-6 _†_
11:6 朝にあなたの種を蒔け。夕方にも手を休めてはいけない。あなたは、あれかこれかどちらが成功するのか、あるいは両方とも同じようにうまくいくのかを知らないのだから。
この御言葉に聞いて、「はい、わかりました。主のお言葉ですからそうします」と歌っているようです。「朝から夕方まで」とは、若き日から年老いるまで、と解釈できますし、あきらめずに失望することなく絶えず、という意味にも解せます。人生とは種蒔きのようなもの。勇気をもって、御言葉を信じて、希望と忍耐をもって日々励みましょう。そこから豊かな実りある人生が生れます。
〈sowing seeds 〉
種蒔きと言うとミレーやゴッホの『種をまく人』を思い出します。
日本キリスト改革派但馬みくに教会の吉田実牧師がご自身の著書にこう書かれてます。
~ 引用 ~
ミレーは「種をまく人」を制作するにあたり、主イエスの「種をまく人のたとえ」(マタイ13:1-23)を意識していたということはほぼ間違いないでしょうが、むしろ、ヨハネ12:24を強く意識したと言われています。
_†_ ② ヨハネ12:24 _†_
12:24 まことに、まことに、あなたがたに言います。一粒の麦は、地に落ちて死ななければ、一粒のままです。しかし、死ぬなら、豊かな実を結びます。
主イエスという一粒の麦は、すでに地に落ちて死んでくださいました。そしてよみがえってくださいました。それは多くの実を結ぶためです。今や主イエスは聖霊において、すぐに心をかたくなにする、弱く、誘惑に負けやすい私たちの心を耕しながら、あきらめることなく御言葉の種をまき続けてくださいます.「わたしがあなたのために十字架についたから、あなたは必ず三十倍、六十倍、百倍の実を結ぶ」とおっしゃりながら、御言葉の種をまき続けてくださるのです。
[参考] 吉田実、『絵画と御言葉 美術作品に表されたキリスト教信仰』、一麦出版社、2018年7月8日第一刷 38章 多くの実を結ぶ 「種をまく人」ジャン=フランソワ・ミレー
~ 引用終わり ~
この吉田牧師の解説を読んで私は、ヨーロッパの古い教会の連続祭壇画をイメージしました。まず、御言葉の種をまき続けるイエス様を描いたミレーの絵があって、その左に続くパネル(額縁)には、「種をまくイエス様」の後に続く大勢の種をまく人々が描かれている!そこで歌われる歌こそ、この讃美歌だ!そんなイメージが私に浮かんできたのです。
本題に戻ります。
〈seeds of kindness〉
このような訳で、私たちも「あなたのお言葉ですからやってみましょう」(ルカ5:5)、と私たちもsowing seedsする訳ですが、その種をseeds of kindness と歌ってます。
「親切の種」ってどういう意味だろうと興味が湧いてきて、真っ先に思い浮かんだのは愛の讃歌として有名な第一コリント13:4です。
_†_ ③ Iコリント13:3-4, 13 _†_
13:3 たとえ私が持っている物のすべてを分け与えても、たとえ私のからだを引き渡して誇ることになっても、愛がなければ、何の役にも立ちません。
13:4 愛は寛容であり、愛は親切(口語訳:情深い、KJV:kind)です。また人をねたみません。愛は自慢せず、高慢になりません。
...
13:13 こういうわけで、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、これら三つです。その中で一番すぐれているのは愛です。
いつまでも残る信仰と希望と愛、この三つの中で一番すぐれている愛のDNAを持つ種を蒔くんだ!と歌っているんですね。
さらにもう一つ。是非とも皆様の記憶に留めていただきたい「親切」があります。旧約聖書ヨシュア記2章に記された、エリコの町を偵察に来たイスラエルの斥候と一人の女性ラハブの遣り取りに出て来る「親切」です。
_†_ ④ ヨシュア記2:12-14 (口語訳)_†_
2:12 それで、どうか、わたしがあなたがたを親切(KJV:kindness、新改訳2017:誠意)に扱ったように、あなたがたも、わたしの父の家を親切に扱われることをいま主をさして誓い、確かなしるしをください。
2:13 そしてわたしの父母、兄弟、姉妹およびすべて彼らに属するものを生きながらえさせ、わたしたちの命を救って、死を免れさせてください」。
2:14 ふたりの人は彼女に言った、「もしあなたがたが、われわれのこのことを他に漏らさないならば、われわれは命にかけて、あなたがたを救います。また主がわれわれにこの地を賜わる時、あなたがたを親切に扱い、真実をつくしましょう」。
この「親切kindness」の結果、ラハブは命を長らえた(ヘブル11:31)ばかりか、イエス・キリストの系図(マタイ1:5)の中では、ルツの夫ボアズの母として紹介されています。この様に、ここで歌われるkindness、聖書のkindnessは、私たちが日常使う「親切」と違っています。
〈Waiting for the harvest, and the time of reaping,〉
この讃美歌では種蒔きと刈り入れが対になっています。農作業では当然のことですが、聖書も同様です。その代表的な御言葉が、
_†_ ⑤ ガラテヤ6:7-9 _†_
6:7 思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種を蒔け(soweth)ば、刈り取り( reap )もすることになります。
6:8 自分の肉に蒔く者は、肉から滅びを刈り取り、御霊に蒔く者は、御霊から永遠のいのちを刈り取るのです。
6:9 失望せずに善を行いましょう。あきらめずに続ければ、時が来て刈り取ることになります。
種蒔きが御霊に助けれた信仰の堅忍に、刈り取りが永遠のいのちに譬えられています。聖書は「種蒔き」と「刈り取り」のモチーフを用いて主イエスの贖いの確かさを教えます。「因果応報」や「善因善果」といったことわざと本質的に違います。主イエスに贖われた私たちなればこそWe shall come rejoicing, bringing in the sheavesです。
■ リフレイン(繰り返し)
Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves,
Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
多くの人が愛唱する詩篇の一つ、詩篇126:6の言葉が何度も繰り返される驚くべき歌詞です。特に自然と心に刻みこまれる歌詞〈bringing in the sheaves〉「束を抱える」とは、主の祝福にあずかることです(参照:詩篇129:7)。
_†_ ⑥ 詩篇126:5-6 _†_
126:5 涙とともに種を蒔く者は喜び叫びながら刈り取る。
126:6 種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰って来る。
126:5 They that sow in tears shall reap in joy.
126:6 He that goeth forth and weepeth, bearing precious(※貴重な、大切な) seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him.
この詩篇126編の時代背景をお話しします。
紀元前500年頃、長期にわたるバビロン捕囚から解放されて祖国に戻ってきたイスラエルの人々により、荒れ果てたエルサレムの町と神殿の再建工事が始められました。しかし、その工事は内憂外患、困難をきわめました(ネへミヤ記)が、そこで神の約束と力に信頼した人々により歌われたのがこの詩篇と言われてます。
その詩篇126編をテキストとするこのリフレインが、『大草原の小さな家』の様々な場面で歌われた如く、アメリカ西部開拓時代(19世紀)の開拓民や伝道者たちはこの讃美歌を高らかに歌い、大いに励まされたことでしょう。
■ 2節
Sowing in the sunshine, sowing in the shadows,
Fearing neither clouds nor winter's chilling breeze;
By and by the harvest, and the labor ended,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
日差しの下でも暗がりの中でも、暗雲たなびこうが寒風吹き荒ぼうが種を蒔きますと歌います。なぜなら私たちは「一切を行われる神のみわざを知らない」(伝道の書11:5)からです。
私たちもこう励まされています。
_†_ ⑦ Ⅱテモテ4:2 _†_
4:2 みことばを宣べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また勧めなさい。
主イエスご自身も、私たちの境遇・環境がどの様であっても、弛まず休むことなく私たちに御言葉を与え続けて下さってます。ミレーがキャンバスに描いた力強い農夫の姿のように。
〈By and by the harvest, and the labor ended,〉
この表現は、終わりの日の刈り入れを宣言する御使いの声が、日一日一日と近づいているのを感じさせます。
_†_ ⑧ 黙示録14:7, 13-16 _†_
14:7 彼(※御使いのひとり)は大声で言った。「神を恐れよ。神に栄光を帰せよ。神のさばきの時が来たからだ。天と地と海と水の源を創造した方を礼拝せよ。」
...
14:13 また私は、天からの声がこう言うのを聞いた。「書き記せ、『今から後、主にあって死ぬ死者は幸いである』と。」御霊も言われる。「しかり。その人たちは、その労苦から解き放たれて安らぐことができる。彼らの行いが、彼らとともについて行くからである。」
14:14 また私は見た。すると見よ。白い雲が起こり、その雲の上に人の子のような方が座っておられた。その頭には金の冠、手には鋭い鎌があった。
14:15 すると、別の御使いが神殿から出て来て、雲の上に座っておられる方に大声で叫んだ。「あなたの鎌を送って、刈り取ってください。刈り入れの時が来ましたから。地の穀物は実っています。」
14:16 雲の上に座っておられる方が地上に鎌を投げると、地は刈り取られた。
だから、We shall come rejoicing, bringing in the sheavesです。
■ 3節
Going forth with weeping, sowing for the Master,
Though the loss sustained our spirit often grieves;
When our weeping's over, He will bid us welcome,
We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
〈Going forth with weeping, sowing for the Master,〉
この3節にも、詩篇126:5にも「涙とともに種を蒔く」とありますが、なぜ泣きながらなのでしょう。
まず理由の一つに、古代オリエントでは、粉にして焼けばパンになる種を地に蒔くことは一時的な飢えを覚悟することだったことです。「あなたのパンを水の上に投げよ。ずっと後の日になって、あなたはそれを見出す。」(伝道の書11:1)との御言葉に従う時も、貴重な糧を無駄にしてしまうかもしれない不安との戦いがあります。それでもこの讃美歌は〈Going forth with weeping, sowing for the Master,〉「主のお言葉ですので」と御言葉に従って種蒔く人の心境を歌っています。
なぜ泣きながらなんだろう...もう一つの理由は三節二行目にあります。
〈Though the loss sustained our spirit often grieves;〉
種蒔きに際してのlossなら、鳥に食べられたり、茨に覆われたり日照りで枯れる種のことでもあるでしょうが、ここでは〈sustain our spirit often grieves〉 「私たちの心をしばしば悲しみに暮れさせる」程の loss だと歌っています。
その様な loss を、ここに集う私たちは知っている、経験済みの筈です。その lossとは、
_†_ ⑨ ピリピ3:7-8 _†_
3:7 しかし私は、自分にとって得であったこのようなすべてのものを、キリストのゆえに損(loss)と思うようになりました。
3:8 それどころか、私の主であるキリスト・イエスを知っていることのすばらしさのゆえに、私はすべてを損(loss)と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失い(loss)ましたが、それらはちりあくただと考えています。…
この聖句は、私たちの信仰がどれ程価値があって尊いものであるかの逆説的表現ですが、キリストを信じるが故に“損失”を被ることは辛いです。物質的損失は言うまでも無く、対人関係での“損失”は私たちの心をえぐります。ですが続けてこう歌います。
〈When our weeping's over〉
_†_ ⑩ ヤコブ5:7-8 _†_
5:7 ですから、兄弟たち。主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は大地の貴重な実りを、初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています。
5:8 あなたがたも耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているからです。
■ むすび
そして 〈He will bid us welcome,〉、私たちはこのみ言葉を聞くことになります。
_†_ ⑪ 黙示録21:3-4 _†_
21:3 私はまた、大きな声が御座から出て、こう言うのを聞いた。「見よ、神の幕屋が人々とともにある。神は人々とともに住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として、ともにおられる。
21:4 神は彼らの目から涙をことごとくぬぐい取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも、叫び声も、苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。」
126:5 涙とともに種を蒔く者は喜び叫びながら刈り取る。
126:6 種入れを抱え泣きながら出て行く者は束を抱え喜び叫びながら帰って来る。
〈We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.〉
主イエスは言われました、「今泣いている人たちは幸いです」(ルカ6:21)
アーメン